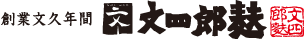芭蕉も触れた、もてなしの心。
今から300年以上前の1689年、ここ六田を俳人・松尾芭蕉と弟子の曾良が訪れました。時は新暦の7月13日。ちょうど、紅花が満開に咲き誇っていたことでしょう。
紀行文『おくのほそ道』にも記されている通り、芭蕉と曾良は、約150日にわたり東北・北陸地方を旅しました。山刀伐峠を越えて山形県尾花沢市に入った芭蕉と曾良は、10泊した後、山形にある「立石寺」に向けて再び歩みを進めるのですが、松尾芭蕉の研究家としても知られる、尾花沢市歴史文化専門員の梅津保一先生によると、『曾良随行日記』の中に、立石寺に向かう途中の六田で、「内蔵に逢、立寄は持賞ス」という一文が出てくると言います。「内蔵」とは、六田にて、今で言う運送業を営んでいた馬車引きの高橋内蔵介のこと。
そして「持賞」とは、ご馳走をいただくことを指すのだそうです。では、なぜ芭蕉が六田を訪れ、高橋内蔵介のもとでご馳走をいただく流れになったのか。それは、芭蕉のかねてからの俳諧仲間である、尾花沢の紅花商人・鈴木清風に薦められたことがきっかけだったようです。当時、六田は宿場町として栄えており、秋田藩佐竹公も参勤交代の際の宿場として重要視していました。ここで、お客様をもてなす心、そして、その土地ならではの美味しいものをご馳走したいという人情の厚さに触れた芭蕉は、立石寺からの帰路、再び六田の内蔵家を訪ねたということです。
ちなみに、ここ六田で産業として麸屋が興ったのは1860年頃と言われています。そのため、芭蕉が訪れた頃はあくまでも各家庭の囲炉裏で、麸を手づくりして食していた程度だと思われますが、いずれにしても、麸の製造に欠かせない美味しい湧水と小麦の栽培に適した土地が六田に揃っていたことは間違いないでしょう。そして実は、芭蕉自身も麸に詳しく、自ら料理する際、献立の中に取り入れることもあったということです。

心を揺り動かす風景との遭遇。
ところで、芭蕉と曾良が六田を訪れた7月上旬というのは、夏の盛りに入る少し前の好天が続く時分。そんな中、東根温泉を過ぎたあたりの道中で突然、季節に似合わぬ白い雪を多くかぶった月山の姿が視界に入ってきた時は、芭蕉もさぞかし驚き、感動したことでしょう。さらに、たくさんの紅花が咲く風景を見るのも初めてだったようで、ちょうど半夏生の頃、最初に1輪だけ花開き、そこから一斉に満開になる紅花の素晴らしい有り様が、芭蕉の俳句の心を揺り動かしたと想像できます。あの有名な「まゆはきを 俤にして 紅粉の花」はそんな背景から生まれた一句ではないでしょうか。そんな風に紅花を愛でる句を詠む一方で、芭蕉は紅花を摘む娘たちを想い、「行く末は 誰が肌ふれむ 紅の花」という句も残しています。
六田の歴史と風土を次の世代へ。
現在私たちは、芭蕉も訪れた六田の歴史や風土を後世に伝えるため、『風に揺らぐ紅花 六田宿』というグループ名で、様々な活動に取り組んでいます。例えば東根中部小学校の子どもたちと一緒に、約150坪の畑に紅花の種を蒔き、収穫して紅花染めをするという総合授業に取り組んだり、毎年7月第2日曜には、芭蕉にちなんだ『まゆはき講演会・コンサート』というイベントを開催。さらに六田麩街道沿いに、芭蕉のブロンズ像や芭蕉が歩いたことを示す道標を設置したり、時には、案内ボランティア役も務めることも。地域の人はもちろん、六田を訪れてくださる観光客の方にも楽しんでいただけたらとても嬉しいですね。
これからも、「よぐござったなっす、ゆっくりしてござっしゃい」というおもてなしの心を大切に、六田の食生活の一部である「麸」の美味しさ、そして六田の風土と人情を皆様に伝えていきたいと思っております。さくらんぼ狩りの際、また芭蕉の足跡を辿る旅の道中に、ぜひ六田の文四郎麸へお立ち寄りください。美しい紅花と共にお出迎えいたします。