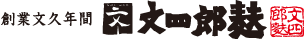羽州街道が通り、宿場町として栄えた六田。旅人たちはひと時の安らぎを求め、六田に立ち寄り、お麸料理をご馳走になり、再び目的地へと向かいました。今もなお、旅の休憩場所として利用される文四郎麸で、和やかな時間を過ごしてみませんか?
今日はページを開いてくださったあなたと一緒に、旅した気分で物語がスタートします。

「まずいっぷくあがらっしゃい」
東根市を通る旧13号線をドライブしていてみつけた「ふ」という大きな看板。気になって入ってみると、そこは江戸時代から続くお麸屋さん「文四郎麸」でした。車麸やおし麸、生麸、お惣菜、おやつまで。目移りするほどたくさんの種類が並ぶ側には囲炉裏端のような休憩スペースがあり、お麸料理の試食が準備されていました。「まずいっぷくあがらっしゃい」。笑顔でお茶を出し、もてなしてくれた女将さん。お茶といっしょに、定番の煮物をご馳走になりました。お麸には野菜やお出汁の旨みがたっぷりしみこんでいて、どこか懐かしく、とても優しい味わいに、体も心も癒されていくようでした。「ここは、むが〜しから旅人たちが休憩をしていったところなんだよ。どうだ?うまいべっす」。初めてきた場所なのに、こんなにも落ち着いてゆっくりできるのは、なぜでしょうか。文四郎麸ではお客様が訪れた時のためにと、毎日お麸料理の試食とお茶、そしてすぐにその作り方を紹介できるよう、レシピを用意しているとのこと。あたたかな心づかいに、誰もが旅の途中立ちよりたくなる気持ちが、分かったような気がしました。

「六田麸は“もったいない”から生まれたんだよ」
山形と聞いて私たちが思い浮かべる特産は、さくらんぼやお米ですが、なぜ東根六田地区ではお麸だったのでしょうか。「それは“もったいない”から始まったんだよ」ちょうど出ていらした文四郎さんが教えてくれました。羽州街道が通り、紅花や葉煙草などを陸路で運ぶ交通の要所となって栄えた東根六田地区。その昔周辺には宿が立ち並び、宿場町として賑わっていたようです。扇状地という土地柄で湧水も豊富。秋田佐竹藩の参勤交代で訪れたお殿様にもおいしいと喜ばれ「佐竹水」とも呼ばれていたそうです。また小麦の栽培地としても適し育てられていて、当時は大変貴重だったため収穫されたものは高級食材として、宿泊者をもてなしていました。「臼で小麦を引いてから調理されるんだけれども、引いて最初に出てくるB品部分があってね。たまたま上方から訪れていた麸焼き職人がそれを見ていて『もったいないからお麸を作ってみてはどうか』と、その技を伝えていったと言われているんです。お麸づくりには欠かせない優れた?水?と?小麦?に加え、技術の伝承。それを守り続けた地域の人柄がお麸を現代に伝えたのだと思います」。


グルテンと小麦を混ぜお麸の生地を作り【写真上】、お麸を焼いている様子【写真下】。作られる工程や、家での料理の仕方を教えてもらいました。
文四郎麸が麸の製造を手掛けるようになったのは、江戸時代、文久年間の頃(1860年〜)。「きっと芭蕉さんもこの道を通って、お麸を食べて行ったんじゃないかな」。長い棒に巻き付けて焼き上げる独特の製法は今も同じで、工場が稼働している日にはその様子を覗くこともできるとのこと。カットされる前の長い車麸をながめながら、ますます興味が湧いてきました。今度は誰かを誘って来てみたくなりました。

文四郎麸の敷地内にある東屋で、湧水受けに使用されていたのは、その昔麦をひくのに使用されていた大きな石臼でした。大人が二人がかりで回していたそうです。

「お麸に糸こんと玉ねぎ、豚バラ肉を入れた煮物」
文四郎麸には、地元で採れた四季折々の食材を使った料理がご馳走になれる「清居」があり、予約をすれば六田ふ懐石料理をご馳走になることができます。もちろん、現代でお麸は日常的な食べ物。さて私にもおいしく作れるでしょうか?「大丈夫、季節の食材と一緒においしくなりますよ。レシピがあるから持って行きなさい」。定番の煮物から唐揚げ、山形で有名な芋煮まで、イラスト付きで分かりやすい様々なレシピを持たせてくれました。では職人でもある文四郎さんが一番大好きなお麸料理は?「それはやっぱりかあちゃんが作る、糸こんと玉ネギ、豚バラ肉の煮物だな。卵に絡めてもよし、ご飯に乗せて丼ぶりにしてもよし、酒のつまみにも。シンプルだけどお麸の味が一番分かるし、何度食べても飽きません」。

この日試食にと準備されていた「煮物」「ごぼうの麸巻き」「麸のからあげ」。調理方法によって全く異なる食感となっており、驚きました。

文四郎麸の駐車場の裏には、訪れる方に楽しんでもらいたいと、文四郎さんが奥様と10年整備し続けているお庭がありました。色とりどりに咲く季節の花、実のなる木。緑の中で爽やかに吹き抜ける風をほほにうけながら、旅の疲れが癒されました。「時代は変わっても、この辺りを通る時には、気軽に寄り道していきたくなるようなお店であり続けたいと願っています。だから毎日、ご馳走とお茶を準備してお待ちしておりますよ」。